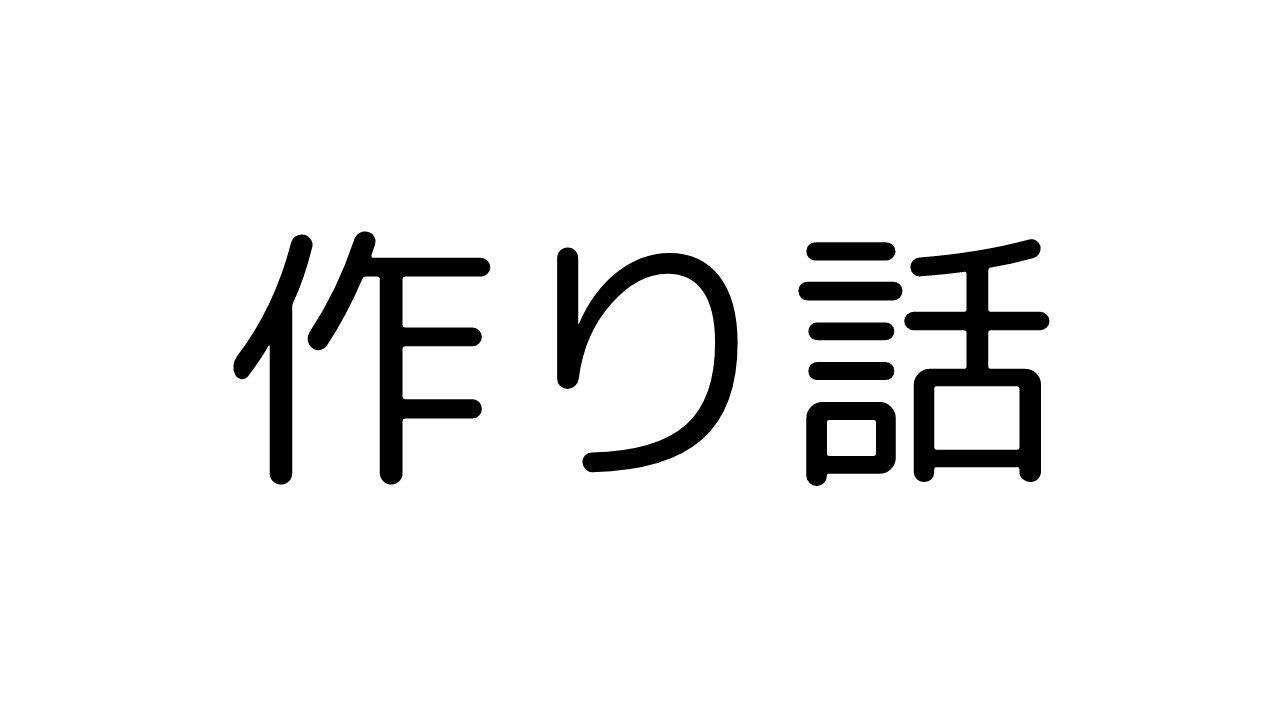もう長らく忘れていたが、小学校に入る前の幼い頃、私は仲が良かった友だちと、二人の老人が住む家に足繁く通っていた。行くようになったきっかけは忘れてしまった。きっと道路でサッカーボールを蹴り合って遊んでいたときに、誤ってボールを庭に蹴り入れてしまったとかそういった類のものだろう。
彼らは私たちにとてもよくしてくれた。遊びに行くといつも美味しいお茶とお菓子を出してくれた。重そうな本を引っ張り出してきて、物語を通じていろいろなところを旅させてくれた。壊れたおもちゃを直してくれたし、私が友人と喧嘩して泣きじゃくっていた日には優しく抱いて胸を落ち着かせてくれた。私が放ったあらゆる疑問に答えてくれる声の温かみが好きだった。彼らにできないこと、彼らが知らないことを探すことのほうが難しかった。いろいろな植物を育てていて、季節の変化とともに家の匂いや色合いも移り変わっていく彼らの家は、まるで魔法使いの家のようだった。
子どもなんて気まぐれなもので、あんなに通っていたのに小学校の中学年に上がった頃には遊びに行かなくなっていた。はっきりとした理由なんて覚えてはいないが、仲の良かった友人と別のクラスになって疎遠になったからとか、サッカークラブに入って忙しくなったとか、そんなあたりだろう。小学生の頃なんて毎日が新しくて仕方なかった。私は目新しいものが好きな子どもだったから、新鮮な刺激を追っているうちに老人の元を訪れることが頭に上がらなくなっていった。
高校生を卒業して地元を離れてしまうとき、なんとなく昔入り浸っていたところを巡っておきたいと思い、記憶を頼りあの老人たちの家も訪れることにした。かつて広いと感じていた、彼らの家へと向かう道路は、18の私にとってやけに狭く感じられた。結局、件の場所にはついたものの、あの家なんて元からなかったよとでもいうように綺麗さっぱりその姿はなくなっていた。更地の端っこには自動販売機がちょこんと立っていた。
私も50になってしまい、基本的にはもう大きな変化のない生活を送っている。最近あった大きな出来事といえば、1週間ほど前に一番下の子どもが家を巣立って行ったことである。日常に穴が空いた寂しさと、更地を見たときの喪失感とが重なったから、今になってこんなことを思い出したのかもしれない。