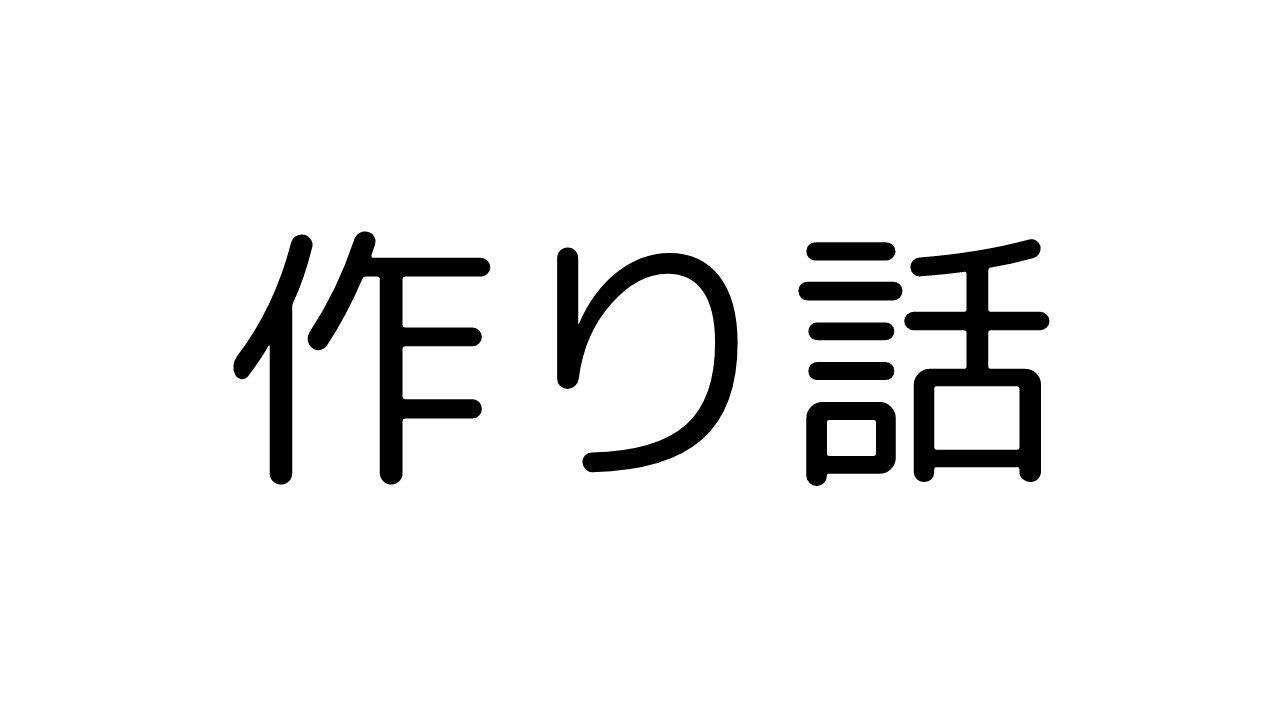あまりにもすることがなかったので、家から少し離れたところにある大きな図書館に行くことにした。館内をふらふら歩きながら、遠い国の昔話でも読んで現実とは違う世界に思いを馳せてもいいかもしれないなという思いに至り、歴史なのか神話なのかよく分からない伝承集を手に取った。
こんな国の話があった。人は生まれた時に12個の白い石と、それを納める木箱とを授けられる。その白い石に額をくっつけると、その時に聞こえる音や目に見える景色、胸のざわめきや背中の汗ばみといった心や身体の情報を保存することができる。記憶の性質に応じて石はその色を変える。保存された石に新たな情報を上書きすることはできないが、その石を額に当てると保存されていた情報を再び感じることができる。
彼らはいつでも幸せを取り逃がさないように小さな袋に入れて石を携帯していた。死人と共に埋葬されるのは、人生を共に生きた石とそれを納めた木箱だった。墓を発掘してみると、埋葬された12個の石のうち、大抵いくつかは白いままだったという。一度きりと言われてしまうと、もったいなくてなかなか使えなかったのだろうか。白いままの石は子孫に譲っても良さそうだが、中途半端な数にして木箱の見栄えが悪くなったままに埋葬することは、埋める側からして気が引けることだったのかもしれない。
それにしても、確かに石によって甘美な記憶を大切に抱えることはできたのだろうが、果たして人々が幸せだったのかどうかは疑問である。人によっては幸せな気持ちを感じたとき、これは石に託しておくべき記憶なのかどうなのかという問いが頭をよぎってしまったのではないだろうか。「ひょっとしたらこれよりも幸せを感じることがありえるかもしれない」と、石を取っておくことに決めたときには、その人の心はきっと冷めてしまっている。目の前の幸せに没入できなくなってしまうのはとても寂しいことのように思える。
余談だが、その国のある地域では墓泥棒が問題になってしまったらしい。盗品の石を売り買いする闇市を想像すると、ある人にとっての幸せがほかの人の幸せと値段という形で比較されている様が目にうかぶ。卑近な俗っぽさを感じて、少しげんなりしてしまった。