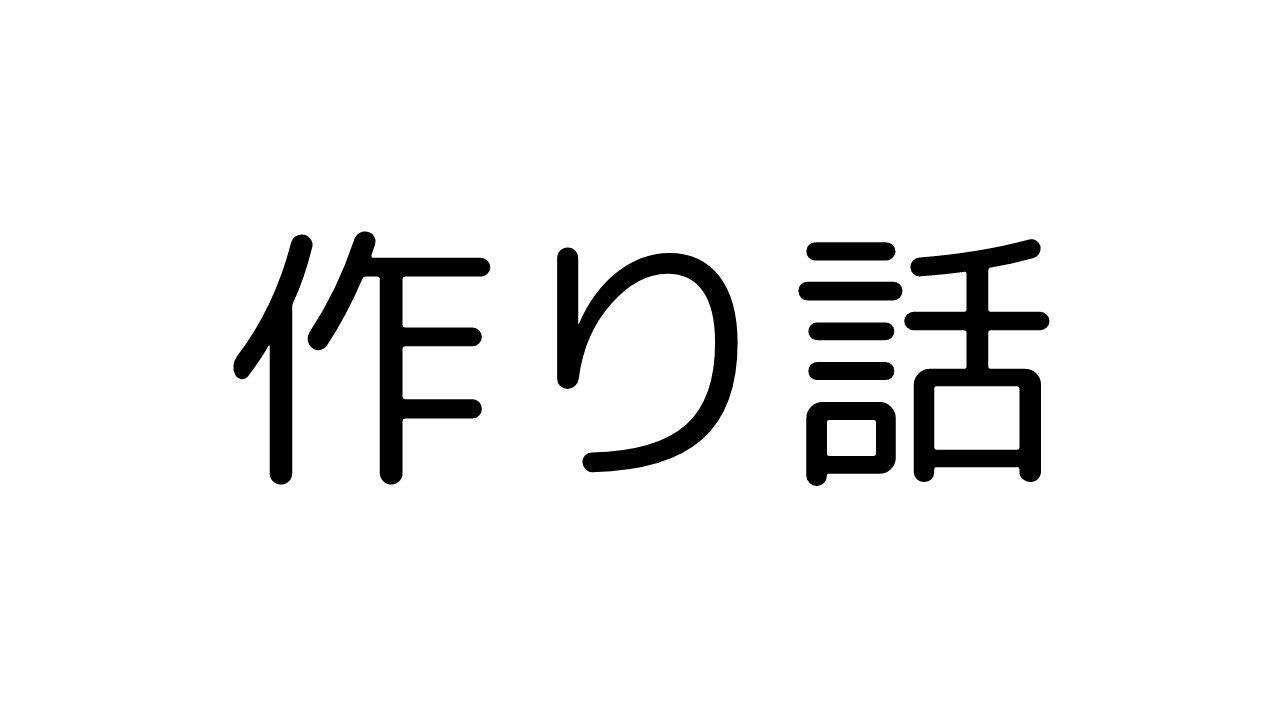「ねぇ、話あるんだけど」
旭はスマホの画面から顔を上げ、面倒くさそうに蓮を見た。嫌な目だ。蓮は一瞬喉をつまらせたが、息を吸い直して言葉を続けた。
「また鞄買ったよね。貯めようってずっと言ってんのに、どういうつもりなわけ?」
旭はわかりやすく大きなため息をついて目を逸らす。その態度が蓮を苛立たせる。
「二人とも稼ぎが大してあるわけじゃないのに、これじゃ引っ越しもできないじゃん。いつまでもこんな狭いワンルームに住み続けるわけにもいかないんだから、いいかげんやめてよ」
「散々言ってるけど、引っ越しなんて別に急ぐ話でもないよね。そんな先のために我慢し続けるなんて、自分にはできないんだけど」
蓮の顔が引きつる。怒りに語気が強くなる。
「急ぐよ。もう27だよ?自分たちだってずっと若いわけじゃないし、結婚だって、子どもだって、ずっと待ってられる話じゃないっていってんでしょ。それに、別にひもじい思いをして暮らそうとまではいってないし、旭が友達と外食に行くことまでいちいち口うるさく止めてるわけじゃないでしょ?そんなに持っててなんの意味があるのかわかんない鞄とか靴とか買うのをやめてっつってんの」
「蓮だって読んでんだか読んでないんだかわかんない本たくさん買ってんじゃん。それに、結婚にも準備とかいろいろあるんだから急かさないで、萎える」
こうなったらいつもと同じだ。お互いの嫌なところをぎゃんぎゃん言い合って、耐えきれなくなったほうが激しくドアを閉めて部屋を出て行くだけ。今日は蓮がその役回りだった。
あんなでも、前はちゃんと好きだったんだけどなと、歩きながら蓮は思った。時刻は17:00を少しすぎたところ。とてもシラフではいられない気分だったが、一人で飲み屋に行くのもばかばかしかった。LINEを開いてトーク履歴を下へと繰り、祐希の名前のところで指を止めた。「呑みに行きたい」と書いて送ると、暇だったのかすぐに「了」と帰ってきた。
蓮と祐希とは高校生の頃からの付き合いで、蓮は美容師の専門学校に、祐希は大学に行ったけれど、お互いの下宿がそんなに離れていたわけではなかったから月に一度くらいの頻度であっては愚痴をこぼして朝まで飲み歩く仲だった。場所はお決まりの繁華街。一軒目は安いチェーンの焼き鳥屋と決まっていた。
「もうやってらんねーよ!」
蓮は勢いよくグラスをテーブルに叩きつけた。ビールの泡がこぼれる。まだそんなに酔っちゃないだろと苦笑しながら祐希がおしぼりを差し出す。
「最近ずっとそんなだから見慣れてもきたけど、あんたの寿命が変な縮み方してないか心配だよ」
「別にこっちだって好きで怒ってるわけじゃないんですけどね」
蓮はグラスをあけておかわりを頼み、焼き鳥を次々に頬張った。旭についてのだらだらとした愚痴を、祐希は適当な相槌を打ちながら流している。
一通り喋ってようやく疲れたらしい蓮が無口になり始めたところで、祐希は口を開いた。
「そんなに嫌いなとこがぽんぽん出てくるのに、よくまだ付き合ってんね」
「だって、もう7年だよ?それに今更誰を捕まえればいいんだよぉ……。職場は別にそんな雰囲気でもないし、お客さんといい感じになるわけでもないし……。」
「……好きな気持ちはまだあんの?」
「……」
正直なところ、もはやよくわからなかった。最近、それぞれの望むあり方の違いがまざまざと見えてきていて、二人で一緒に日々を送っている将来像がまるで思い浮かばなかった。それでも長く過ごしていれば情も湧いているし、何より恋人がいるというステータスを手放す踏ん切りはそう簡単につかなかった。惰性と言ってしまえばそうだった。
蓮が大きくため息をつくのを聞いて、祐希は言った。
「クラブでもいって飲み直すか」
「……それ、悪くないかも」
もやついた気持ちはまだ嫌な感じのまま残っているし、クラブで遊ぶことを旭への当てつけとしてやりたい気持ちもあった。二人は店を出て繁華街の奥の方へと向かった。
内臓を揺らすような重低音が響き、人の匂いと汗とが相まってむしむしとした空気が立ち籠めていた。前の方では出来上がって気持ちよくなった兄ちゃん姉ちゃんたちが楽しそうに踊り、輪の中心から少し離れた場所で静かに体を揺らしている人もいれば、端の方で人目も憚らずにいちゃついているカップルもいる。
ドリンクカウンターで甘めの酒を買い、しばらくは二人で音楽に乗って体を揺らしていたが、じきに祐希は「ごめん、前の方行くわ!」と言ってイカつい方々の中に入っていってしまった。祐希にはああいう奔放さがある。人と楽しく時間を過ごすのが上手い人だから、高校にいたときも大学にいたときもよくモテていた。ただ、長続きしているところを見たことがない。飽きっぽくて、いつも刺激に飢えている。同じ人と一緒にいるよりもいろんな人と関わっているのが好きなんだろうな、きっと。
祐希のことだ、今日もきっと誰かといい感じになって、自分のことをおいて寝に行くんだろうなと蓮はため息をついた。一気にドリンクを飲み干し、プラカップをゴミ箱に放りこんだ。もう少し飲みたい気分だと思ってバーカウンターに足を向けたとき、一人で静かにドリンクを飲んで座っている人と目が合ってしまった。
「ヤバいかも」と思った時には遅かった。蓮の中で何かが弾けた。あまりにも顔が良かった。酔いが回っているのもあったのだろうけれど、思わず立ちすくんでしまった。その人はこちらを見て微笑んだ。吸い寄せられるように近づいていくことしかできなかった。いい匂いがした。
鈍く輝いた相手の目は蓮をぬるく求めていたし、蓮もまた同じ眼差しを向けていた。
「何か飲む?」
その声は蓮の鼓膜を心地よく撫でた。
「……あなたの好きなものがいい」
ドリンクを飲みながら、二人は静かに音楽を聞いていた。蓮はちらちらと相手に目線をおくった。どうしようもないほどに、タイプだった。
「行こう」
蓮は手を取られた。振り返れば、前の方で踊り続けている祐希が蓮に手を振っていた。蓮は顔を前に向けて、取られた手を握り返した。
あーあ、寝ちゃうんだろうな。ざまあみろ、旭。自分みたいないい人を適当に扱ったからこんなことになるんだ。せいぜい悔めばいいさ。
街の夜は長い。二人は手を繋いだまま、光輝く電灯の渦の中へと溶けていった。