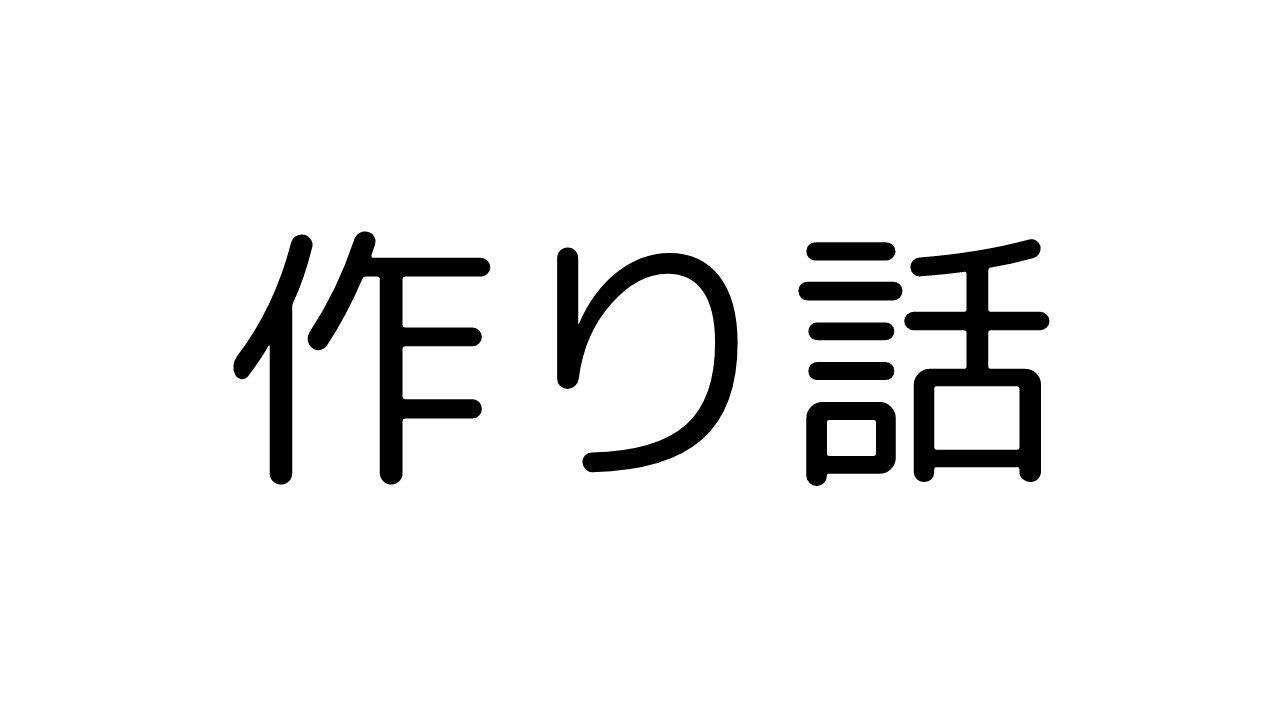その子は生まれた時から人の頭上に砂時計が見えた。ただしそれは不完全な砂時計だった。上部はろうとのようになっていて、上から下へと流れた砂は何にも受け止められることなく外へさらさら流れ出るしかない、そんな形をしていた。砂時計の大きさや装飾は人によって違っていたし、残されている砂の量も人によって違っていた。
その子は人の砂時計を眺めることが好きだった。砂の色は人によって様々で美しかったし、外へと流れ出る砂が空気にきらきらと溶けていく様は綺麗だった。しかし次第にじっくりと眺めることはなくなっていった。それは、その子が他者の頭上を見つめ続けていると周囲の人々が訝しむためであった。その子は聡かったので、まじまじと見ることも、人に話すこともなんとなくいけないなことなのだろうと感じるようになり、だるまさんがころんだで遊ぶように、こっそりと人の砂時計を眺めるようになった。
その子が砂時計の表す意味になんとなく気がついたのは、優しかった祖父や祖母が眠りから目覚めないでいるのを見たときだった。彼らの頭上の砂時計にはもはや何も残ってはいなかった。
幼稚園くらいの頃からその子には気掛かりがあった。父の砂時計に残されている砂の量が、父と同い年の母や、友達の親のそれよりもやや少ないのだ。今すぐ尽きてしまうほどに少なかったわけではないが、それでもどこかもやっとした不安を感じずにはいられなかった。
小学校に上がったときには、その子の不安はより一層深刻なものになっていた。父に残された砂は、幼稚園の時の半分くらいにまで減ってしまっていたのだ。他の人々と比較しても明らかに減りが早かった。父の砂時計には少しひびが入っていたし、父は笑うことが減って部屋でこもりがちになっていた。母は以前よりも仕事に出る時間が長くなった。心配をかけまいと気を張っているようだったけれど、明らかに疲れていた。母の砂時計の口から溢れる砂は少し濁っていた。その子の心は日々じくじくと傷んでいた。
その子は道ゆく人の砂時計を密かに日々観察していたのだが、ある時からとある小さな建物が気になっていた。その建物は、砂時計のガラスにひびが入っていたり、明らかに砂の量が少なかったりするような、元気のない人たちがぽつぽつと足を運び、しばらくするとさっきよりも綺麗になった砂時計を浮かべて、さっきよりも生気を纏って出てくる、そんな場所だった。
その子は幼かったので、一人で得体の知れない建物に入っていくことに不安を感じずにはいられなかったが、もうそんなことも言ってられなかった。その子は深呼吸をして呼び鈴を押した。しばらくして、建物の奥からゆっくりとした足音が聞こえてきた。音は近い場所で止まり、扉が静かに開いた。そこには一人の老人が立っていた。
老人は静かにその子を迎え入れた。足を踏み入れた先、居間のような空間には、二つのソファが向かい合うようにして置かれており、その間には年季の入ったテーブルがあった。老人はその子をソファに座るように促して、麦茶の入ったグラスとお菓子の入った小さなかごをテーブルに置いた。
老人は無口だったし、その子も言葉がうまく出てこなかったので黙っていた。それでも居心地の悪さはなかった。深く息を吸ってみるとその部屋には柔らかな匂いが漂っていた。そしてまたその部屋には、外の車の音はあまり聞こえないけれど、完全には無音ではないような心地よい静けさがあった。
麦茶を飲んで、お菓子を食べているうちに心が解けてきたのか、その子は自然と言葉を繋ぎ始めた。これまでに何度か、元気のなさそうな人がこの建物に入り、その後に少し元気な顔をして外に出てくるのを見たこと、そして、自分の父の調子が良くないこと、一緒にいる母も苦しそうであること、そんな両親を見ていると自分も辛くなること、どうにか父に、そして母に元気になってほしいと思っているということを、ゆっくりと話した。老人はそれを静かに聞いていた。少し考えているようだった。老人はしばらくの沈黙ののちに、ついてきなさいと言って立ち上がった。その子は数歩離れて老人の後ろを歩いた。老人がこちらを向いていない隙に、老人の砂時計を眺めてみた。決して新しくはないけれど、落ち着いた輝きをしているガラスだった。砂の量は見た目の年齢にしては多い方で、老人の髪の色と同じような白い色をしていた。
老人に続いて足を踏み入れたその部屋は、小さな作業場であった。雑然とした空気が漂い、無骨な器材が転がっていた。机にも床にも論文のような紙の束がどっさりと積まれていた。その子はしげしげと部屋の様子を眺めていたけれど、老人に声をかけられて我に返った。老人の手には使用感のある革の手袋がはめられていた。
老人はその子の前に立って、目を閉じてゆっくり息を吸うようにと言った。その子は言われた通りに深呼吸をした。思いの外、空気に埃っぽさはなかった。しばらく深呼吸を続けていると、自分の頭の少し上に老人が手をやっている気配を感じた。数秒後、ことりと机の上に何かが置かれる音がした。老人は目を開けるようにといった。その子が目を開けると、机の上には一つの砂時計が置かれていた。
老人はその子に、砂時計が見えるのだろうと問いかけた。その子は頷いた。老人は静かに、これがあなたの砂時計なのだと伝えた。
その子は砂時計を見ることができたけれど、砂時計が鏡に映ることはなかったので自分のものを見るのはこれが初めてだった。新しくて、ガラスはつやつやとしていた。口から薄い黄緑色をした砂がさらさらとこぼれては空気に溶けていった。ただ、小さなひびが入っていることが気に掛かった。まだ砂が漏れ出るほどには割れていないけれど、そうなるのも時間の問題であるように見えた。
老人はその子の頭を撫でた。髪越しに感じる手袋の感触はごわごわとしていたけれど、嫌な感じはしなかった。老人はその子に、頑張ったねと小さく言って頭から手を離した。老人は机の上に置かれたその子の砂時計をしばらく見つめていた。
老人は壁際の棚から空っぽの砂時計を取り出し、その子の砂時計の隣へと置いた。二つの砂時計の上蓋を開けて、やや大きい銀色のスプーンで、黄緑の砂を少しずつ空っぽの砂時計へと移し始めた。さっきまで空っぽまでだった砂時計の口からも黄緑の砂が外へと静かに流れ出始めた。老人は静かに口を開いて、砂の流れを止めてはならないのだと呟いた。砂を移しおわると、老人は先ほどの棚から茶色の大きなつぼを取り出した。老人は筆を手に取り、その先を壺の中へと浸した。それは透明な水飴のようだった。老人はその子の砂時計のガラス部分を台座から取り外し、ひび割れた部分に静かに透明な液体を塗り重ね、手袋をつけた手で表面をならした。その作業が終わると再びスプーンを手に取って、緑色の砂をもとの砂時計へと戻して上蓋を閉めた。ひびは綺麗に塞がっていた。
老人はその子に向かって再び目を閉じて深呼吸するようにと言った。その子は砂時計が元の位置に戻されるのを感じながら呼吸をしていた。目を開けて、息を吸ったその子は、先ほどまでにはなかったような穏やかさを胸に感じていた。老人はゆっくり居間へと戻った。その子もその後に続いた。
老人はその子にお茶を差し出し、静かに話し始めた。
人は常に少しずつ砂を使って生きている。人によって生まれた時点での砂の量も違えば、一日生きるために必要とする砂の量だって違う。同じ人であっても、元気があれば少しの砂を使うだけで生きていけるけれど、少し息を吸うのにも困難を感じるほどに弱っているときには必要な砂の量だって増える。
砂時計のガラス部分も、日々少しずつ姿を変える。沢山の砂を必要とするときにはそれに応じて口が開いていくし、それほど要らなくなれば口はすぼんでいく。その質だって日々変わる。ゆとりがある時にはしなやかに伸び縮みするけれど、少しの変化でひびが入ってしまうくらいに脆くなってしまうことだってある。
老人は始めから砂時計が見える人だった。それでも手に取ることはできなかった。割れ目から砂をぼろぼろとこぼしている人がいても、ただ見ることしかできなかった。老人は苦しく耐え難かったので、砂時計に触れるための手袋と、割れ目を埋めるための透明な液体を発明した。ただ、砂を作ることだけはどうしてもできなかった。
その子は、砂時計を修理したら人は元気になるのかと尋ねた。老人は眉間に皺を寄せて、そう簡単な話でもないと答えた。修理をしたとしても、その人が直面している問題が解決するわけではない。その人の心を弱らせる原因があり続ける限り、修理しても砂時計はじきに壊れてしまう。それでも修理するのは、一時的にでも立ち直ることができなければ、状況を変えるための手を打つことすらも難しくなってしまうからだ。砂時計の修理は完全な解決策ではない。しかしそれでも、必要な人にとっては必要なものなのだ。
老人は重ねて言った。自分は砂を作ることができなかった。やはり砂だけは他人が作り出すことのできるものではないようだ。そしてまた、一度使った砂が戻ってくることもない。しかし、砂が残ってさえいれば、本人次第ではそこから砂を増やしていくことはできる。だから、砂を使い切って倒れてしまう前に、砂時計を修理して、こぼれる砂の量を減らして、砂の量を少しずつ戻していけばいい。砂時計にひびが入ってしまったとしても、人は立ち直ることができる。そのくらいの強さを人は持っている。
一連の話を聞き終えたのち、その子は老人に両親をここへ連れて来たいと言った。老人は静かに頷いた。
その子は父の部屋の前に立った。扉をたたいて父を呼んだ。会ってほしい人がいる、その人と話したらきっと心が軽くなる、元気になるのだと言った。返事はなかった。どうして出てきてくれないのかと問い、扉を開けてほしいと言った。それでも返事はなかった。その子が扉を叩く力は少しずつ強くなり、言葉にも嗚咽が混じるようになっていった。台所から飛び出してきた母も、その子のあまりの剣幕を前に、ただ見つめることしかできなかった。その子の手は赤く傷んでいるようだったけれど、止めることなどとてもできそうになかった。その子は、どうしても死んでほしくない、いなくならないでほしい、また顔が見たい、私を抱きしめて欲しいと叫んだ。叫んで、扉をたたいた。何度も何度も強く強くたたいて、たたき疲れて、へたり込んで、泣いた。
部屋の扉は開いた。父は戸惑いというより心配の表情を浮かべていた。彼はもちろん彼であったが、やはり確かにその子の父であったのだ。父は顔をぐちゃぐちゃにしているその子をみて、腰が抜けたように地面に座り込んだ。彼の頬骨は浮き出て、ひげも髪も伸びて、背中は猫のように丸まって、肌はひどく青白かった。それでも彼の眼は、やはり彼が優しい父であるのだとその子に確信させるものだった。その眼で十分だった。その子は父の服に顔を埋めて泣いた。様子を見ていた母も、抱きつかれた父も泣いていた。
父は外に出すには獣のような臭いがしすぎていたから、その子は父をぐいぐいと風呂場へ連れて行った。父が風呂に入っている間に、母にもついてきてほしいと言った。母は戸惑っているようだったが、その子の眼をじっとみて、頷いた。
三人一緒に外に出るのは久しぶりのことだった。父の着ている服の襟首は伸び切ってしまっていたけれど、そんなことはその子にとってどうでもいい話だった。またこうやって歩けることがただただ嬉しかった。
じきに三人は老人の家に着いた。老人はまた麦茶を出して迎え入れた。
お茶を飲んでお菓子を食べているうちに、場の空気は解けていった。穏やかな雰囲気ではあったけれど、父はうまく言葉を紡ぐことができないようだった。老人はその子に、少しの間作業場で待っていてくれないかと伝えた。その子は自分の両親がどのような状態にあるのかを知りたかったから当然拒んだけれど、両親の眼も訴えてくるものだからしぶしぶ折れて奥の部屋へと移動した。
その子はのけものにされたことに対してしばらく不貞腐れていたが、泣いた疲れが残っていたのか、次第にとても強い眠気に包まれていった。数分後には作業場の片隅で壁にもたれかかって眠りについていた。
老人に声をかけられてその子は眼を覚ました。老人は二つの砂時計を机の上に置いて、その子の修理をしたときと同じように丁寧に作業を始めた。老人の所作は綺麗だったし、見ているその子を安心させた。
修理を終えた老人は、その子を連れて両親のいる部屋へと戻った。老人は二人に、静かに眼を閉じて深く息をするように言った。老人は、二人がそうしている間に砂時計を頭の上へそっと戻して、眼を開けるようにと伝えた。二人の眼は先ほどよりもすっきりとしているようだった。両親は老人に礼をいい、その子を連れて建物を後にしようとしたが、老人は少しその子を引き留めた。その子の頭に手を置いて、小さく「きっと大丈夫だから」と呟いた。今度こそ三人は建物を後にした。老人は静かにそれを見送っていた。
その子は老人の元を毎日のように訪れては家族の様子を話した。父が病院に通うようになったこと、三人で夕食を食べるようになったこと、母が家の外で悩みを話せる友人を見つけたこと、父も母も砂時計に大きな異常がないこと、心なしか父の砂の量が増えていること、そうはいっても疲れてしまって一日中眠っている日もあるということ。老人は決まって静かに話を聞いていた。
その子がいつものように老人の元を訪れたある日、珍しく老人の方から口を開いた。道具がなくたって、砂時計の修理はできる。人に寄り添い、静かに声を聞き、食べるものを用意してあげられたなら、そのうち割れ目は塞がるし、砂の量も増える。だから自分にとって大切な人が元気をなくしていて、それがひどく辛く感じられるのであれば、静かに一緒に居るようにしたらいい。それが一番いい修理方法なのだから。
なんだか普段より喋るものだから、その子は少し驚いた。でもとても大切な話のように思えたから、覚えておこうと思った。その子が建物を出るとき、老人はその頭をそっと撫でた。何を言うでもなかった。髪の毛越しに感じる老人の手は温かかった。
次の朝、その子には異変が起こっていた。砂時計が見えないのだ。父を見ても母を見ても、頭の上には何もない。家を飛び出して街ゆく人を眺めても、学校で友人たちを眺めても、何もなかった。
学校が終わるや否や、その子は老人のところへと走った。呼び鈴を鳴らしてしばらく待つけれども気配がない。そっと扉に触れると、それはひとりでに開いた。部屋の中には何もなかった。その部屋はすっかり引っ越しが済んでしまったようで、老人の痕跡はなかった。
その子は足を踏み入れて、壁にもたれながら座り込んだ。しばらくぼんやりとしていたけれど、ふとある考えが頭をよぎった。あの老人はひょっとしたら神様だったのかもしれない。だとしたらずいぶんとお人好しで不器用な神様だ。天から人を眺めていればよかったのに、胸を痛めて、わざわざ降りてきて、ひっそりと人を癒していたのだから。
髪を切った翌日は鏡を見て驚くけれど、三日もしたら馴染む。砂時計もそんなものなのだろうか。そんなことをぼんやりと思いながらその子は立ち上がって、服についた埃をはたいた。そしてどこに行ってしまったかわからないあの老人が、これからも穏やかに過ごしていけることを願った。その子は扉を開けて外に出ようと思ったけれど、その前に立ち止まって深く息を吸ってみた。仄かな残り香を感じたような気がした。